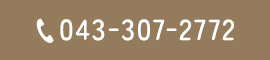- 胃酸などが食道に上がってくる逆流性食道炎
- 逆流性食道炎の症状と原因
- 逆流性食道炎になりやすい人は?
- 逆流性食道炎とストレスの関連性は?
- 逆流性食道炎の検査
- 逆流性食道炎の治療・改善について
- 逆流性食道炎の症状を和らげる食事
胃酸などが食道に上がってくる逆流性食道炎
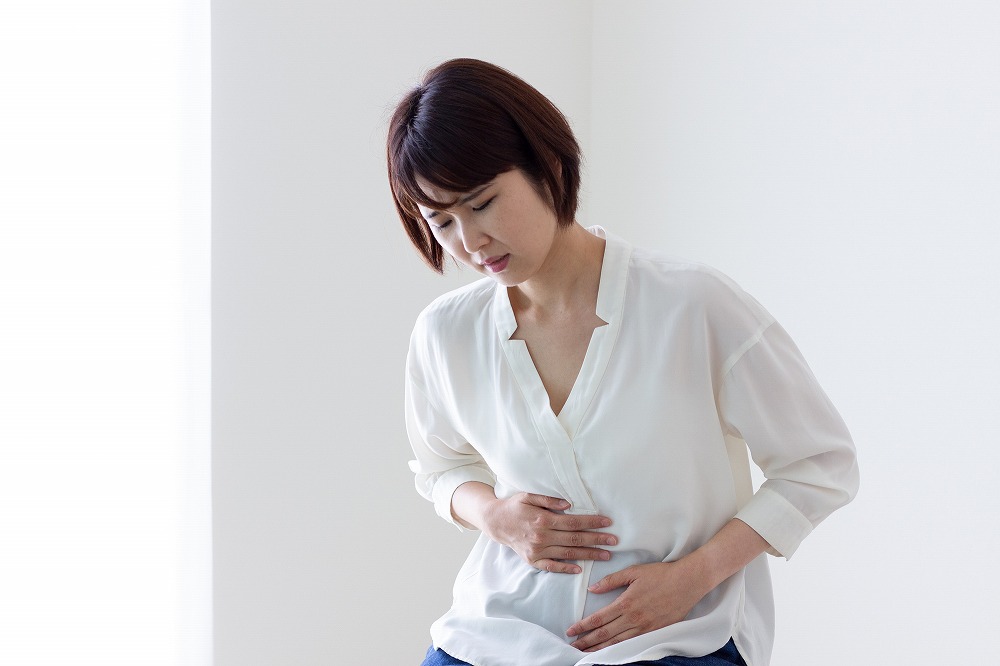
逆流性食道炎は、胃の中の消化物が食道に逆流し、炎症を引き起こす疾患です。胃酸が食道を傷つけることで慢性的に炎症が起こり、症状が悪化すると日常生活に支障をきたすこともあります。成人の約10~20%が発症しているとされ、特に中高年層に多く見られます。以前は日本人には少ない疾患とされていましたが、近年は生活習慣の変化などにより増加傾向にあります。
逆流性食道炎の症状と原因
症状
逆流性食道炎の症状として、以下が挙げられます。
- 胸やけ
- 呑酸(酸っぱい液体が喉や口まで上がる)
- みぞおちや胸の痛み、不快感
- 喉のつかえ感
- 腹部膨満感
- げっぷが頻繁に出る
- 乾いた咳が続く
- 声が枯れる
これらの症状は、特に空腹時、夜間、横になった時などに強くなりがちです。
原因
食道と胃の境目には、胃の内容物が逆流しないように働く「下部食道括約筋」という筋肉があります。この筋肉が緩むと、胃の内容物が食道へ流れ込みやすくなります。
下部食道括約筋は、老化や早食い、暴飲暴食、高脂肪の食事、肥満、または締め付けの強い服装による腹圧の上昇などが原因で緩むことがあります。
逆流性食道炎になりやすい人は?
逆流性食道炎になりやすい特徴を持つ方は以下のとおりです。
- 脂っこい食事やアルコール、炭酸飲料の過剰摂取
- 食べ過ぎや早食いの習慣がある
- 喫煙習慣がある
- 腹部を締め付ける服をよく着る
- 食べてすぐ横になる習慣がある
- 畑仕事などで長時間前屈みの姿勢をとる
- 内臓脂肪型肥満の方
- 腰が曲がっている方
逆流性食道炎とストレスの関連性は?
胃酸の分泌は自律神経によって制御されていますが、ストレスによって自律神経が乱れると胃酸の分泌量やタイミングに異常をきたし、逆流性食道炎を引き起こしやすくなります。したがって、ストレス管理も重要です。
逆流性食道炎の検査
 逆流性食道炎の診断には問診と合わせて胃カメラ検査が用いられます。胃カメラ検査では、食道粘膜の状態を直接観察できるため、逆流性食道炎だけでなく、食道がんなどの食道疾患の診断にも有効です。検査の結果次第で、胃酸を抑える薬の処方などを行い、経過を観察します。
逆流性食道炎の診断には問診と合わせて胃カメラ検査が用いられます。胃カメラ検査では、食道粘膜の状態を直接観察できるため、逆流性食道炎だけでなく、食道がんなどの食道疾患の診断にも有効です。検査の結果次第で、胃酸を抑える薬の処方などを行い、経過を観察します。
逆流性食道炎の治療・改善について
逆流性食道炎の治療には、以下の3つの方法が取られます。
生活習慣の改善
生活習慣の改善として次の手段が挙げられます。
- 食べ過ぎない
- 食後すぐに横にならない
- 就寝の2時間前までに夕食を済ませる
- 高脂肪、高糖分、アルコールなど刺激の強い食べ物を控える
- 減量(肥満の方)
- 便秘解消
- 禁煙
- 締め付けが少ない服装を選ぶ
薬物療法
薬物療法では、胃酸の分泌を抑制する薬を使用し、症状の緩和を図ります。薬は医師の処方に従って適切に服用することが重要です。
手術療法
生活習慣の改善や薬物療法で効果がみられない場合、外科的治療が考慮されます。この治療法は医師と相談し、慎重に検討する必要があります。
逆流性食道炎の症状を和らげる食事
下記の食べ物は胃酸過多になりにくいため、意識して摂るようにしましょう。
油を使わず、煮る・蒸す・茹でるといった調理法がおすすめです。
- おかゆ
- 柔らかく炊いたご飯
- 豆腐
- 白身の魚
- 食パン(味付けの濃いパンや加工パンを除く)
- ヨーグルト
- うどん
- 鶏ささみ
- 牛乳