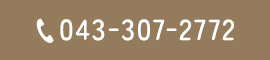過敏性腸症候群とは
過敏性腸症候群は、胃や小腸、大腸に器質的な異常が見られないにも関わらず、腹痛や下痢、便秘などの腹部症状が続く疾患です。この疾患は、精神的なストレスなどが引き金となり、自律神経のバランスが崩れることで腸の働きに異常が生じて発症します。男性は30~40代、女性は20~50代に多く見られます。最近では、10代の若年層にも増加しています。日本人の約10〜15%の方が過敏性腸症候群に罹患していると言われています。
過敏性腸症候群のタイプ
便通の状態によって過敏性腸症候群は以下のタイプに分類されます。
便秘型
便秘症状が主で、排便が週に3回以下、強くいきまないと排便できない、残便感がある、コロコロした便が出るなどの特徴があります。ストレスが溜まると便秘の症状が悪化することがあります。
下痢型
下痢症状が主で、腹痛の後に水様便や泥のような軟便を繰り返す、排便回数が多いなどの特徴があり、緊張を感じると腹痛や便意が強くなります。
混合型
便秘が長く続いたかと思うと下痢になり、下痢が治まると再び便秘になるといったように、便秘と下痢を交互に繰り返すタイプです。
分類不能型
便表面にヒビが入るような硬めの便や、ちぎれるような軟便が見られることがありますが、便の状態に大きな問題はありません。膨満感や腹鳴、おならなどガスに関連する症状を起こすこともあります。
過敏性腸症候群の原因
はっきりとした原因は分かっていませんが、細菌・ウイルスによる感染性胃腸炎にかかった後や精神的なストレスがある場合に発症しやすいとされています。抗生剤の使用や体調の変化による腸内環境の悪化も一因と考えられています。
腸には多くの神経細胞があり、自律神経を介して脳とつながっているため、腸と脳は相互に影響し合っています(脳腸相関)。腸が不調だと気持ちが落ち込み、脳に受けたストレスは腸に反映し不調を招きます。排便に対して高い理想を持ち、なかなか自分の排便に納得できないと過敏性腸症候群を発症しやすくなります。排便の回数や症状は個人差が大きいため、過度に理想を求めないことが重要です。
過敏性腸症候群の検査
 過敏性腸症候群を診断するためには、まず自覚症状や排便の状態を確認し、既往症、生活習慣、ストレスの有無などについて問診を行います。血液検査や大腸カメラ検査を実施し、腸にがんや炎症などがないか確認します。
過敏性腸症候群を診断するためには、まず自覚症状や排便の状態を確認し、既往症、生活習慣、ストレスの有無などについて問診を行います。血液検査や大腸カメラ検査を実施し、腸にがんや炎症などがないか確認します。
過敏性腸症候群の治療
薬物療法、食事療法、生活様式の調整を主に行います。
薬物療法
消化管の働きを調整する薬や腸管の内容物を調整する薬が用いられます。過度のストレスが原因の場合は、精神面の健康に対処するために抗不安薬や抗うつ薬を使用することも検討されます。
食習慣の改善
刺激物や冷たいものを避け、腹八分を心がけて食事を摂りましょう。毎日決まった時間に食事を取ることで、体のリズムを整えます。暴飲暴食でストレス解消をしないようにしましょう。
生活習慣の改善
十分な睡眠と休息を取り、喫煙している方は禁煙に努めましょう。毎朝、便意がなくてもトイレに行く習慣をつけることで、排便が規則的になることが期待できます。
ストレスの対処法
ストレスは完全に解消することは難しいですが、減らすためにできることを見つけて実行することが大切です。趣味や旅行、スポーツ、音楽、読書など、楽しめることを見つけてストレスを解消しましょう。