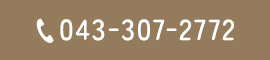炎症性腸疾患について
 炎症性腸疾患は、体の免疫システムの異常により腸管に慢性的な炎症が生じ、腹痛、下痢、血便などの症状が現れる疾患の総称です。潰瘍性大腸炎とクローン病が代表的です。いずれも完治する治療法がないため、厚生労働省に難病指定されていますが、炎症をコントロールする治療を行うことで、通常の生活を送ることが可能です。早期に診断し、適切な治療を開始することが重要です。
炎症性腸疾患は、体の免疫システムの異常により腸管に慢性的な炎症が生じ、腹痛、下痢、血便などの症状が現れる疾患の総称です。潰瘍性大腸炎とクローン病が代表的です。いずれも完治する治療法がないため、厚生労働省に難病指定されていますが、炎症をコントロールする治療を行うことで、通常の生活を送ることが可能です。早期に診断し、適切な治療を開始することが重要です。
潰瘍性大腸炎とは
 潰瘍性大腸炎は、大腸の粘膜に炎症が生じ、びらんや潰瘍ができる疾患で、厚生労働省から難病に指定されています。約22万人の患者さんがいると推定されており、年々増加しています。発症年齢は10〜20歳代が最も多いとされていますが、小児や高齢者に発症することもあります。下痢や血便などの症状は、症状のある活動期と症状の落ち着いた寛解期を繰り返し、様々な合併症を伴うことがあるため適切な治療を継続することが重要です。自己判断で治療を中断すると症状が悪化することがあるため注意が必要です。適切な治療により症状をコントロールすることができれば、健常人と変わらない生活を送ることが可能です
潰瘍性大腸炎は、大腸の粘膜に炎症が生じ、びらんや潰瘍ができる疾患で、厚生労働省から難病に指定されています。約22万人の患者さんがいると推定されており、年々増加しています。発症年齢は10〜20歳代が最も多いとされていますが、小児や高齢者に発症することもあります。下痢や血便などの症状は、症状のある活動期と症状の落ち着いた寛解期を繰り返し、様々な合併症を伴うことがあるため適切な治療を継続することが重要です。自己判断で治療を中断すると症状が悪化することがあるため注意が必要です。適切な治療により症状をコントロールすることができれば、健常人と変わらない生活を送ることが可能です
潰瘍性大腸炎の原因
はっきりとした原因は特定されていません。食事やストレス、腸内細菌の乱れなどの刺激(環境的要因)に対して上手く適応できない体質(遺伝的素因)を持つ方が、何らかのきっかけにより大腸の免疫が過剰に反応し自己の大腸粘膜を傷つけてしまう、という機序ではないかと考えられています。
潰瘍性大腸炎の症状
- 下痢・粘液便
- 粘血便
- 便意とともに強くなる腹痛(しぶり腹)
重症化した際の症状
- 夜間も続く頻回の水様の下痢
- 多量の血便
- 強い腹痛
- 発熱
- 体重減少
- 貧血
潰瘍性大腸炎の合併症
炎症が腸壁の深くまで広がると、大量の出血や穿孔、狭窄を引き起こすことがあります。また、強い炎症が継続することで大腸の動きが止まりガスや毒素が溜まる中毒性巨大結腸症も危険な合併症です。このような合併症を起こすと緊急手術が必要になることもあります。腸管以外にも目や皮膚、関節に合併症が現れることがあります。また、長期間炎症が続くと、大腸がんのリスクが高まるため、適切な炎症のコントロールと定期的な大腸カメラ検査を受けることが大切です。
潰瘍性大腸炎の検査・診断
 問診で自覚症状を詳しく確認し、血液検査で炎症や貧血の程度、栄養状態のチェックを行います。大腸カメラ検査は確定診断を行うために必須の検査です。特徴的な粘膜の炎症所見の有無を調べ、炎症の範囲や程度を把握します。必要に応じて、粘膜の組織検査(生検)や培養検査を行います。炎症の活動期での検査は苦痛を伴うことが多いため、当院では、鎮静剤を適切に使用することで苦痛の少ない検査を行っています。
問診で自覚症状を詳しく確認し、血液検査で炎症や貧血の程度、栄養状態のチェックを行います。大腸カメラ検査は確定診断を行うために必須の検査です。特徴的な粘膜の炎症所見の有無を調べ、炎症の範囲や程度を把握します。必要に応じて、粘膜の組織検査(生検)や培養検査を行います。炎症の活動期での検査は苦痛を伴うことが多いため、当院では、鎮静剤を適切に使用することで苦痛の少ない検査を行っています。
潰瘍性大腸炎の治療
残念ながら現時点では完治を目指す治療法は確立されていません。そのため、早期の寛解導入と長期の寛解維持により生活の質を保つことを目標に治療を行います。
まずは5-ASA製剤を使用して炎症を抑えます(寛解導入)。5-ASA製剤で改善しない場合は、ステロイド、免疫調整薬、生物学的製剤などを段階的に使用し寛解導入を目指します。薬物治療が奏功しない場合や合併症を併発した場合には手術療法を選択することもあります。
寛解期にも、寛解維持のため5-ASA製剤、免疫調節薬、生物学的製剤を状態に合わせて使用します(寛解維持)。
寛解期の日常での注意点
寛解期には、炎症の再燃を防ぐため、治療を中断せず継続することが大切です。また、腸に負担をかけない生活習慣を心がけましょう。
食事
暴飲暴食や過食、刺激物、冷たい物は控え、下痢を引き起こしやすい食物を避けましょう。
運動
特に制限はありませんが、無理のない範囲で行いましょう。
睡眠
ストレスや睡眠不足などによる自律神経の乱れは潰瘍性大腸炎を悪化させることがあるため、生活リズムを整え、十分な睡眠をとり、疲れやストレスが溜まっている時はしっかり休息をとることが大切です。
妊娠・出産
寛解期が続く場合は妊娠や出産が可能です。しかし、服薬を止めると症状が悪化する可能性があるため、妊娠がわかった時点で服薬を中止するのではなく、必ず主治医と相談してください。
クローン病
クローン病とは
 クローン病は、大腸や小腸などの消化管が炎症を起こし、下痢、腹痛などの症状をきたす疾患で、厚生労働省から難病に指定されています。はっきりとした原因は不明ですが、遺伝的要因、食事や腸内細菌などの環境要因、免疫機能の異常が病気の発症に関わると考えられています。特に、脂質や糖質の過剰摂取(ファストフード)や喫煙の関連が指摘されています。約5万人の患者さんがいると推定されており、年々増加しています。発症年齢は10代後半から30代前半が多いとされています。クローン病は、腸管の狭窄、膿瘍、瘻孔などの入院や手術を必要とする合併症をきたすことがあるのが特徴です。適切な治療を行うことにより、入院や手術になるリスクを下げることが可能で、症状の落ち着いた状態(寛解)を維持できれば一般の生活を送ることが可能です。
クローン病は、大腸や小腸などの消化管が炎症を起こし、下痢、腹痛などの症状をきたす疾患で、厚生労働省から難病に指定されています。はっきりとした原因は不明ですが、遺伝的要因、食事や腸内細菌などの環境要因、免疫機能の異常が病気の発症に関わると考えられています。特に、脂質や糖質の過剰摂取(ファストフード)や喫煙の関連が指摘されています。約5万人の患者さんがいると推定されており、年々増加しています。発症年齢は10代後半から30代前半が多いとされています。クローン病は、腸管の狭窄、膿瘍、瘻孔などの入院や手術を必要とする合併症をきたすことがあるのが特徴です。適切な治療を行うことにより、入院や手術になるリスクを下げることが可能で、症状の落ち着いた状態(寛解)を維持できれば一般の生活を送ることが可能です。
クローン病の原因
クローン病の原因として、遺伝的な要因が関与するという説、細菌やウイルスによる感染症説、食事の中の何らかの成分が腸管粘膜に異常な反応をひきおこしているという説、腸管の微小な血管の血流障害説などが報告されてきましたが、はっきりと証明されたものはありません。最近の研究では、なんらかの遺伝的な素因を背景として、食事や腸内細菌に対して腸の免疫細胞が過剰に反応して病気の発症、増悪にいたると考えられています。
クローン病の症状
クローン病の症状は炎症が起きている部位によって異なりますが、主に以下の症状が見られます。
- 下痢
- 腹痛
- 血便
- 発熱
- 体重減少
- 痔瘻
- 肛門周囲膿瘍
口内炎、関節炎、皮膚症状、眼症状など腸管以外の臓器に合併症が生じることもあります。
クローン病の検査と診断
 血液検査で炎症や貧血の程度を調べ、栄養状態を把握します。内視鏡検査(胃カメラや大腸カメラ検査)で消化管粘膜の状態を直接観察します。炎症の程度や範囲を把握するとともに、粘膜を採取し病理学的な診断を行います。クローン病は炎症が小腸に発生することも多いため、小腸造影検査や小腸内視鏡検査、カプセル内視鏡検査を行うこともあります。
血液検査で炎症や貧血の程度を調べ、栄養状態を把握します。内視鏡検査(胃カメラや大腸カメラ検査)で消化管粘膜の状態を直接観察します。炎症の程度や範囲を把握するとともに、粘膜を採取し病理学的な診断を行います。クローン病は炎症が小腸に発生することも多いため、小腸造影検査や小腸内視鏡検査、カプセル内視鏡検査を行うこともあります。
クローン病の治療
クローン病は、残念ながら治療により完治する病気ではありません。早期に炎症を鎮静化し(寛解導入)、その状態を維持すること(寛解維持)により、瘻孔や狭窄といった合併症を防ぎ生活の質を保つことが治療の目標です。自覚症状が改善したため治療を中断してしまうと再燃することも多いため、症状のない寛解期にもしっかりと治療を続けていくことが大切です。
栄養状態の改善、腸管の安静、食事からの刺激を除くため、アミノ酸主体の栄養剤の内服や点滴をします。食事による刺激を抑えるため、低脂肪・低残渣の食事がすすめられます。
薬物治療は、5-ASA製剤、ステロイドや免疫調整薬、生物学的製剤(抗TNF-α抗体製剤など)を状態に合わせて使用します。高度の狭窄や瘻孔などの合併症に対しては手術治療が行われます。