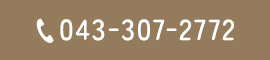胃炎について

胃炎は、胃の粘膜に炎症が起こっている状態で、急性胃炎と慢性胃炎に大別されます。急性胃炎は、アルコールの過剰摂取、食べ過ぎ、喫煙、ストレスなどが主な原因となります。これに対し、慢性胃炎はピロリ菌感染が主要な原因であり、次に非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の副作用が関与しています。特にピロリ菌感染が関与する場合、除菌治療によって再発リスクを大幅に減少させることが可能です。慢性的な炎症が続くと、胃がんリスクが高まる萎縮性胃炎が進行することもあるため、早めに消化器科を受診することが推奨されます。なお、胃がんは症状だけでは胃炎と区別しにくいため、軽い症状が続く場合でも医師に相談することが重要です。
解消のための適切な治療
慢性胃炎は、胃粘膜に炎症が見られるケースと、炎症がなく症状だけが現れるケースに分けられます。後者のケースは、消化管の機能低下や知覚過敏が原因と考えられる機能性ディスペプシアの可能性が高いです。ピロリ菌感染陽性の場合、除菌治療が成功することで萎縮性胃炎の進行を防ぎ、胃がんリスクを抑えることが期待できます。一方、機能性ディスペプシアは消化器科での専門的な診断と治療が必要です。慢性的な胃炎の症状に苦しむ場合は、原因を特定するためにも消化器科への受診がすすめられます。
胃炎の種類と原因
急性胃炎
急性胃炎は、過剰なアルコール摂取、喫煙、カフェインや唐辛子などの刺激物の摂取によって胃液の分泌が過剰になり、胃粘膜が炎症を起こす状態です。また、ストレスなどで自律神経が乱れることも急性胃炎の原因となります。
慢性胃炎
ピロリ菌感染
慢性胃炎の原因のほとんどはピロリ菌感染です。ピロリ菌が胃内で毒素を生成し、胃粘膜を傷害し続けることで慢性的な炎症が生じます。ピロリ菌は周囲の胃酸を中和するため、胃内での生存が可能です。抗生剤による除菌治療が推奨されます。
非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の副作用
市販薬にも含まれることがあるNSAIDsの成分により、数回の服用でも胃炎を引き起こすことがあります。胃潰瘍などの重篤な疾患を引き起こす場合もあるため、薬の服用後に胃炎の症状が出た場合は早めに消化器科に相談することが大切です。
萎縮性胃炎
胃粘膜は通常、ダメージを受けても修復されますが、修復が追いつかなくなると胃粘膜が薄くなる萎縮性胃炎に進行します。さらに進行すると、胃粘膜が腸の粘膜のようになる腸上皮化生が起こり、一部ががん化して胃がんの発症につながることがあります。
機能性ディスペプシア
機能性ディスペプシアは、消化管の機能低下や知覚過敏が原因で胃痛や胃もたれ、ムカつきなどの症状が起こりますが、胃粘膜に炎症などの器質的な問題はありません。自律神経の影響を受けるため、ストレスや生活習慣が症状に関与することが多く、専門的な診断と治療が必要です。
胃炎の主な症状
急性胃炎
- 胃痛、みぞおちの痛み
- 胸やけ
- 吐き気
- 腹部の不快感
- 腹部の張り・膨満感
- 黒いタール状の便
慢性胃炎
※萎縮性胃炎も同様の症状を起こします
- 胃痛、みぞおちの痛み
- 胃のむかつき
- 胸やけ
- 吐き気
- 胃が重い
- 腹部の張り、膨満感
- 食欲不振
慢性胃炎は症状が軽度でも長期間続く場合が多く、気づかないうちに萎縮性胃炎へと進行することがあります。
市販薬で一時的に症状が解消できても、薬を止めると再発する場合は消化器科の受診が推奨されます。また、家族に胃がんやピロリ菌感染陽性の方がいる場合、無症状でもピロリ菌感染や胃粘膜の状態を確認するために医師の診察を受けると安心です。
萎縮性胃炎と胃がん
萎縮性胃炎は、胃炎が長期的に続いた結果、胃粘膜が薄くなる状態であり、前がん病変とされています。慢性の胃炎が進行すると、胃粘膜が腸粘膜のように変化する「腸上皮化生」を引き起こし、その一部ががん化することがあります。特に注意が必要なのは、腸上皮化生の段階になると胃環境が悪化し、ピロリ菌の生息も困難になるため、ピロリ菌感染検査が陰性でも胃がんのリスクは高いままであることです。このため、ピロリ菌が陰性でも定期的な胃カメラ検査を受け、胃がんの早期発見に努めることが重要です。
ピロリ菌感染が確認された場合、除菌治療によって萎縮性胃炎への進行を防ぎ、繰り返す胃炎症状を抑えることが可能です。ただし、除菌治療に成功したとしても、胃がんリスクを完全に排除することはできないため、年に一度の定期的な胃カメラ検査が必要です。
胃炎の検査
 急性胃炎の場合は、問診を通して飲酒、食事内容、薬の服用状況などを確認し、原因に合わせた治療を行います。原因が特定できない場合には、胃カメラ検査を実施し、胃粘膜の状態を確認します。
急性胃炎の場合は、問診を通して飲酒、食事内容、薬の服用状況などを確認し、原因に合わせた治療を行います。原因が特定できない場合には、胃カメラ検査を実施し、胃粘膜の状態を確認します。
慢性胃炎の場合には、問診の後、胃カメラ検査とピロリ菌感染検査を行い、炎症の範囲や萎縮の有無を把握します。必要に応じて組織を採取し、病理検査やピロリ菌感染検査を行って確定診断を行います。当院では、高度な内視鏡システムを使用し、専門医が正確な検査を行っております。また、鎮静剤を用いることで、身体への負担を大幅に軽減した胃カメラ検査が可能です。
胃炎の治療
胃炎の主な症状は、胃酸分泌抑制薬や粘膜保護薬などを適切に使用することで短期間で改善が見込めます。ただし、炎症が完全に治るまでは、指示に従って服薬を継続することが重要です。また、ピロリ菌が陽性の場合、除菌治療を行うことで症状の再発を防ぎ、胃がんなどのリスクを減らすことができます。
NSAIDsの副作用で胃炎が発生している場合には、服用薬の変更が有効ですが、疾患によっては薬の変更が難しいケースもあるため、消化器科での継続的な治療を行い、胃粘膜のダメージを最小限に抑えることが大切です。
薬物療法
胃酸分泌抑制薬や粘膜保護薬など、症状やライフスタイルに合わせた処方を行います。市販薬で一時的に症状が改善しても、胃がんなど他の疾患と症状が類似しているため、自己判断せず胃カメラ検査を受けることが重要です。
ピロリ菌の除菌治療
ピロリ菌除菌には、2種類の抗生物質と胃酸分泌抑制薬を1週間服用する治療が行われます。ピロリ菌が抗生物質に耐性を持つ場合、除菌が失敗することがありますが、抗生物質を変えて2回目の治療も可能です。除菌治療の成功率は1回目が85〜90%、2回目を合わせると95~98%となります。判定は服薬終了から1か月程度経過後に尿素呼気試験や便中ピロリ抗原測定により行います。
除菌治療が成功すれば胃粘膜の炎症再発を抑え、萎縮性胃炎の進行を防ぐことで胃がんリスクを低下させる効果が期待できます。ただし、胃がんリスクを完全に排除するわけではないため、定期的な胃カメラ検査が必要です。
生活習慣の改善
胃粘膜の炎症リスクを軽減するため、過度な飲酒や喫煙、唐辛子やカフェインの摂取を控えることが推奨されます。また、暴飲暴食や不規則な食事、睡眠不足を避け、規則的な生活を心がけましょう。