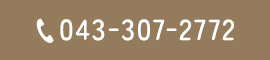このような症状がある方は
ご相談ください
- 3日以上排便がない
- 市販の下剤を使っても便が出ない
- 便秘が続いて吐き気がする
- 排便時に血が混じっている
- 強い腹痛がある
- 排便後も不快な残便感がある
- 排便時に肛門が切れて出血する
便秘とは
 便秘は、3日以上排便がない状態、または毎日排便があっても残便感がある状態です。排便時に強くいきむ必要があったり、硬便である場合も便秘とされます。便秘は老若男女問わず起こり、慢性化している方も少なくありません。放置すると腸の働きに不調をきたし、さまざまな二次的症状を引き起こす可能性があるため、早期の対策が重要です。
便秘は、3日以上排便がない状態、または毎日排便があっても残便感がある状態です。排便時に強くいきむ必要があったり、硬便である場合も便秘とされます。便秘は老若男女問わず起こり、慢性化している方も少なくありません。放置すると腸の働きに不調をきたし、さまざまな二次的症状を引き起こす可能性があるため、早期の対策が重要です。
便秘の原因
便秘の原因は人それぞれで、大きく分けて機能性便秘(3種類)と器質性便秘(1種類)の4つに分類できます。
運動不足や無理なダイエットが原因の弛緩性便秘
腸管の緊張がゆるみ、腸のぜん動運動が十分に行われなくなることで起こる便秘です。便が長時間大腸内にとどまり、水分が過剰に吸収されて硬くなってしまいます。女性や高齢者に多く、便が硬くなり、排便時に痛みが生じます。その他にも腹部膨満感や食欲低下、肌荒れ、肩こり、イライラなどの症状が現れることがあります。運動不足、水分や食物繊維不足、ダイエット、腹筋の低下などが原因となります。
ストレスなどが原因のけいれん性便秘
精神的ストレスや過敏性腸症候群などが原因で、腸が過度に緊張して便がうまく運ばれなくなり便秘を引き起こします。便がコロコロとした形になり、食後に下腹部痛や残便感が生じることがあります。また、便秘と下痢が交互に起こることもあります。
高齢者に多い直腸性便秘
便が直腸に達しても排便反射が起こらず、直腸に便が停滞して排便できなくなる便秘です。高齢者や寝たきりの人に多く、排便を我慢することが原因となります。
下剤の使用NGの器質性便秘
腸閉塞や大腸がん、腸管癒着などの器質的な障害部分に便が引っかかり、通過障害が起きて生じる便秘です。この場合、下剤を使うと腸管穿孔を引き起こすリスクがあるため、使用は避けるべきです。早めの受診が必要です。
便秘に関連する疾患・症状
排便時の力みが原因の「痔」
便秘が続くと排便時に力みすぎて、肛門周囲の静脈がうっ血していぼ痔(痔核)ができたり、肛門上皮が切れて切れ痔(裂肛)を引き起こすことがあります。痔があると排便をためらってしまい便秘を悪化させる、という悪循環に陥りやすいです。
手術が必要なケースもある「大腸憩室症」
大腸憩室症は、大腸の壁に袋状のへこみ(憩室)ができる疾患です。便秘により腸管内圧が高まることで生じます。通常は無症状ですが、憩室の血管が破れて出血したり、憩室内に細菌が感染して大腸憩室炎を引き起こすことがあり、重篤な場合は手術が必要となる場合もあります。大腸憩室症予防のために便秘の解消は大切です。
高齢者に多い「滞留便」
滞留便とは、便秘で排出されず腸内に長く留まっている便のことです。便は本来なら体外に排泄されるはずの老廃物です。それを溜め込むことで、腸内に悪玉菌が増えたり、ガスが過剰に発生して腸内環境の悪化につながります。また、水分が吸収されて便が硬くなることでさらに排便を困難にします。便秘による便の滞留はさらなる便秘を引き起こす要因となります。適切な便通コントロールが重要です。
肌トラブルやむくみの原因にも
便秘で腸内環境が悪化すると有害物質が産生され、腸から血中に吸収されて全身に運ばれます。これを皮膚から体外へ排泄しようとするため、肌に負担がかかりニキビや肌荒れを引き起こします。また、便秘による腸の血流の悪化は全身の血流低下にもつながります。余分な水分が体外に排泄されないため、むくみにつながる可能性があります。
便秘の検査
便秘の検査では、腹部レントゲンでどれだけ腸内にガスや便が溜まっているかを調べたり、大腸内視鏡検査で大腸がんなどの器質的疾患がないかを精査します。
便秘の治療法
便秘の治療は、食物繊維や水分を十分にとることが基本です。加えて、適度な運動を行い、排便の習慣をつけ、ストレスを発散することも重要です。薬物治療では、状態に合わせた薬剤の調整を行います。
食事のリズムを整える
朝昼晩の3食をしっかりと取ることが大切です。特に朝食は便意を促すきっかけとなるため、毎日必ず摂取しましょう。
食物繊維や水分を十分にとる
食物繊維は腸のぜん動運動を高め、便を排出しやすくします。穀物や豆類、果物、ひじき、寒天などを意識的に摂取するようにしましょう。また、水分が不足すると便が硬くなり、排便が困難になりますので、十分な水分摂取が重要です。朝起きてコップ1杯の水を飲むことで、その日排便を促進します。
腸内環境を整える食品を積極的にとる
乳酸菌を含むヨーグルト、納豆などの発酵食品、玄米や大豆などに含まれるオリゴ糖などは腸内環境を整え、便秘を解消する効果があります。日常の食事に取り入れるとよいでしょう。
適度な運動をする
運動不足が便秘の大きな原因です。特に体力や筋力が低下すると、便秘が悪化します。腹筋を鍛えることや、お腹のマッサージを習慣化することで腸を刺激し、排便を促進する効果が期待できます。
薬物治療
大腸を刺激して蠕動運動を高めることで排便を促す刺激性下剤、腸に水分を集めて便を柔らかくすることで排便を促す非刺激性下剤があります。腸内環境を改善するため整腸剤も有効です。便秘の状態にあった薬を選択することが重要です。
それでも便秘が続く場合は
早めの来院を
週に1〜2度のお通じがあり、症状が軽度であれば、食事や生活改善、市販薬によるセルフケアで改善が可能です。しかし、便秘には適切な薬の選択が必要です。消化器科では、患者さんの状態に合わせたお薬を選ぶだけでなく、新しいタイプのお薬もご提案できます。これらのお薬は、従来のものに比べて効き目が持続しやすい点が特徴です。慢性的な便秘や合併症でお困りの方、これまでの治療で効果を感じられなかった方は、一度ご相談ください。